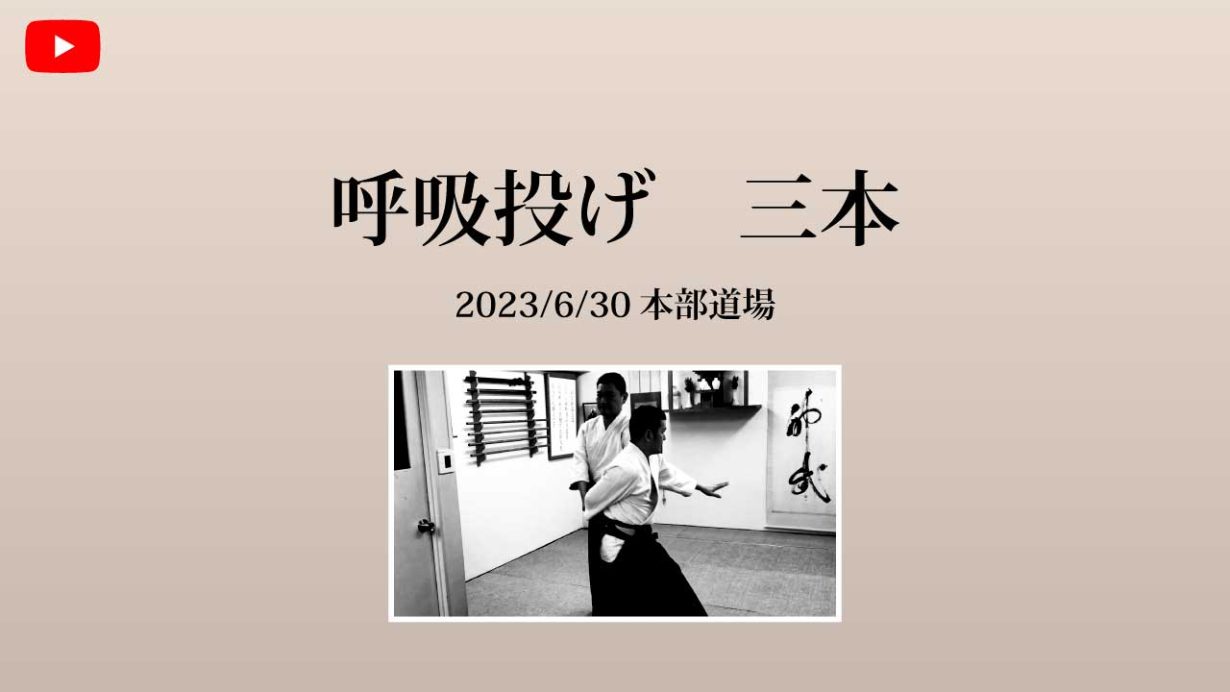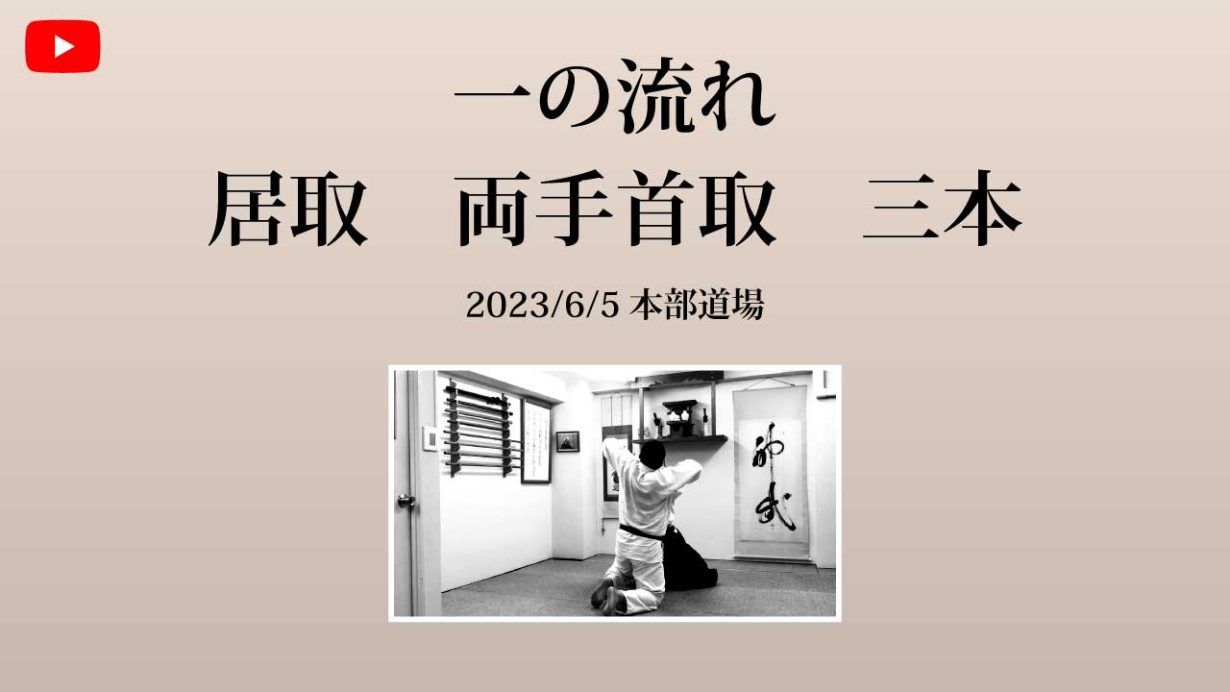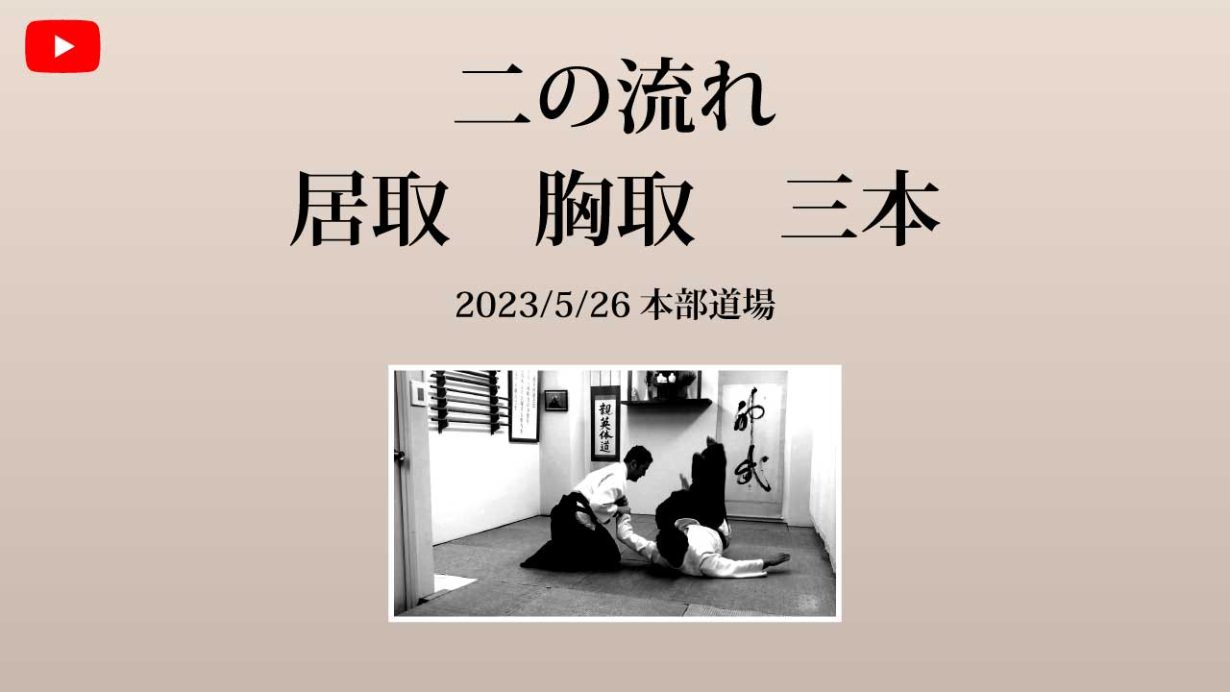本日、親英体道 本部道場において以下の稽古をしました。
「一の流れ 半座半立 片手首取横 三本」
半座半立ちは、身体の硬さを取り、立ち技へ移行するためのお稽古として取り組んでおります。
受け身を取るお稽古を単体で親英体道は行いません。
それは、親和力の中で、受けも取りもなく、『受け身』という事は起こらないからです。
ですから、上の段位の人は、下の段位の人が『気の流れ』において転がれるように下手に立って深い気遣いが求められます。
特に初心者の方と組む場合は細心の注意が必要です。
これが『気を練る』ことになり胆力の養成に繋がります。
これは独りではお稽古出来ないので道場で一緒に勉強しましょう。